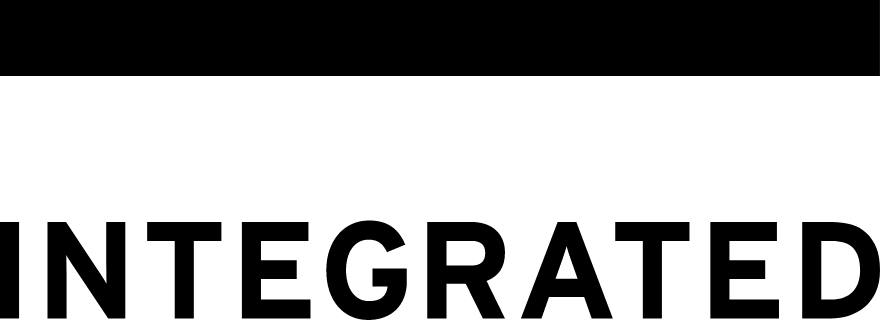学生の課題作品
-
hoge
![]()
![]()
1年 描写
「 ワイヤーを使って立体物を作る 」 -
hoge
![]()
![]()
1年 プロダクト
「 ソルト&ペッパー 」 -
hoge
![]()
![]()
1年 描写
「 私の夏休みを描く 」 -
hoge
![]()
![]()
1年 描写
「 石と他の素材を組み合わせて描く 」 -
hoge
![]()
![]()
1年 描写
「 ワイヤーを使って立体物を作る 」 -
hoge
![]()
![]()
1年 プロダクト
「 空間演習[空間の構成] 」 -
hoge
![]()
![]()
1年 グラフィック
「 デザインバイアクシデント 」 -
hoge
![]()
![]()
1年 グラフィック
「 動作とコミュニケーション 」 -
hoge
![]()
![]()
1年 プロダクト
「 ソルト&ペッパー 」 -
hoge
![]()
![]()
1年 描写
「 風景(上野毛キャンパス)を描く<セザンヌを考えて> 」 -
hoge
![]()
![]()
1年 インターフェース
「 コミュニケーションの設計 」 -
hoge
![]()
![]()
1年 描写
「 静物を描く 」 -
hoge
![]()
![]()
1年 グラフィック
「 形態演習2 [デザイン・バイ・アクシデント] 」 -
hoge
![]()
![]()
1年 プロダクト
「 イメージとかたち 」 -
hoge
![]()
![]()
1年 プロダクト
「 イメージとかたち 」 -
hoge
![]()
![]()
1年 プロダクト
「 ソルト&ペッパー 」 -
hoge
![]()
![]()
1年 プロダクト
「 段ボール椅子 」 -
hoge
![]()
![]()
1年 プロダクト
「 段ボール椅子 」 -
hoge
![]()
![]()
1年 選択基礎演習Ⅰ 表現
「 ワイヤードローイング 」 -
hoge
![]()
![]()
1年 選択基礎演習Ⅰ 表現
「 ワイヤードローイング 」 -
hoge
![]()
![]()
1年 インターフェース
「 コミュニケーションの設計 」 -
hoge
![]()
![]()
1年 インターフェース
「 コミュニケーションの設計 」 -
hoge
![]()
![]()
1年 インターフェース
「 WS[新しい読み方] 」 -
hoge
![]()
![]()
1年 インターフェース
「 WS[新しい読み方] 」 -
hoge
![]()
![]()
1年 インターフェース
「 WS[軌跡の可視化] 」 -
hoge
![]()
![]()
1年 インターフェース
「 WS[軌跡の可視化] 」 -
hoge
![]()
![]()
1年 グラフィック
「 構成による視的メッセージ 」 -
hoge
![]()
![]()
1年 選択基礎演習Ⅰ 表現
「 キーワード風景画 」 -
hoge
![]()
![]()
1年 選択基礎演習Ⅰ 表現
「 ヌードドローイング 」 -
hoge
![]()
![]()
1年 選択基礎演習Ⅰ 表現
「 人体を描く(ヌード着彩) 」 -
hoge
![]()
![]()
1年 選択基礎演習Ⅰ 表現
「 現代の浮世絵を描く 」 -
hoge
![]()
![]()
2年 描写
「 金属(アルミ板)で立体物を作る 」 -
hoge
![]()
![]()
2年 ダイアグラム
「 データ・ドローイング 」 -
hoge
![]()
![]()
2年 ダイアグラム
「 ノーテーション 」 -
hoge
![]()
![]()
2年 描写
「 金属(アルミ板)で立体物を作る 」 -
hoge
![]()
![]()
2年 ダイアグラム
「 ノーテーション 」 -
hoge
![]()
![]()
2年 写真
「 小さな彼女 」 -
hoge
![]()
![]()
2年 インタラクション
「 新しい音の出し方 」 -
hoge
![]()
![]()
2年 造形技法
「 傘 」 -
hoge
![]()
![]()
2年 造形技法
「 傘 」 -
hoge
![]()
![]()
2年 描写
「 浮世絵を意識して東京を描く 」 -
hoge
![]()
![]()
2年 描写
「 浮世絵を意識して東京を描く 」 -
hoge
![]()
![]()
2年 描写
「 人物(女性像)を描く 」 -
hoge
![]()
![]()
2年 造形技法
「 皿 」 -
hoge
![]()
![]()
2年 図
「 ダイアグラム[Notation] 」 -
hoge
![]()
![]()
2年 図
「 ダイアグラム[Notation] 」 -
hoge
![]()
![]()
2年 造形技法
「 機能と仕組みと行為とかたち
」 -
hoge
![]()
![]()
2年 造形技法
「 機能と仕組みと行為とかたち 」 -
hoge
![]()
![]()
2年 造形技法
「 機能と仕組みと行為とかたち 」 -
hoge
![]()
![]()
2年 相互作用
「 開いたり閉じたりして見る写真
」 -
hoge
![]()
![]()
2年 情報編集
「 好きなものを図解で説明する 」 -
hoge
![]()
![]()
2年 文字
「 「文明と文字」演習/彫る 」 -
hoge
![]()
![]()
2年 文字
「 「文様と文字」演習/押し転がす 」 -
hoge
![]()
![]()
2年 観察
「 行動の観察
」 -
hoge
![]()
![]()
2年 文字
「 「文明と文字」演習/彫る 」 -
hoge
![]()
![]()
2年 文字
「 「文明と文字」演習/彫る 」 -
hoge
![]()
![]()
2年 観察
「 無意識の行動、行為の痕跡 」 -
hoge
![]()
![]()
2年 観察
「 無意識の行動、行為の痕跡 」 -
hoge
![]()
![]()
2年 観察
「 無意識の行動、行為の痕跡 」 -
hoge
![]()
![]()
2年 観察
「 無意識の行動、行為の痕跡 」 -
hoge
![]()
![]()
2年 写真
「 写真作品 」
1・2年次の課題と作品
1年次では、問題を発見して具現化のための独自の視点を手に入れるための「みる」技術と、アイデアを美しく具現化させるための造形技術を鍛えるため、グラフィックデザイン、プロダクトデザイン、インターフェースデザインといった4つの視点で授業を行います。色彩や形態、構成といった造形の基礎に加えて、更に動作や時間、視覚以外の知覚がもたらすビジュアル・コミュニケーション、構造や機構を伴った立体構成の知識とその制作スキル、「情報」という直接は目に見えないものについての扱い方について課題制作を通じて学んでいきます。また、デッサンやドローイングなどの描写や立体造形・素材研究などを行うための選択制の演習も実施し、骨太な表現力を身に着けます。2年次には、日常の気付きや問題の提起に対し、表現メディア、媒体、物体や環境あるいはその組み合わせのうち相応しい表現方法を選択しながら、適正なデザインへ導くためのプロセスを理解します。そのために、観察、図、文字、情報編集、相互作用、造形技法、写真といった演習を通じ、アイデアを具体化するさまざまなスキルを修得します。
-
hoge
![]()
![]()
3年 深澤・長崎プロジェクト
「 リブ 」 -
hoge
![]()
![]()
3年 柴田プロジェクト
「 既知の表現効果を用いたゲームのデザイン 」 -
hoge
![]()
![]()
3年 柴田プロジェクト
「 既知の表現効果を用いたゲームのデザイン 」 -
hoge
![]()
![]()
3年 柴田プロジェクト
「 既知の表現効果を用いたゲームのデザイン 」 -
hoge
![]()
![]()
3年 柴田プロジェクト
「 既知の表現効果を用いたゲームのデザイン 」 -
hoge
![]()
![]()
3年 永井プロジェクト
「 何かと何かを掛け合わせて新しいデザインを作る 」 -
hoge
![]()
![]()
3年 イラストレーション演習
「 連作・11枚以上 」 -
hoge
![]()
![]()
3年 空間演出
「 外と内緩やかな境界 」 -
hoge
![]()
![]()
3年 中村プロジェクト
「 ふたつの動きのコンポジション 」 -
hoge
![]()
![]()
3年 形体制作
「 CLOCK 」 -
hoge
![]()
![]()
3年 インフォメーション
「 Network|つながりの可視化 」 -
hoge
![]()
![]()
3年 中村プロジェクト
「 表象のデザイン 」 -
hoge
![]()
![]()
3年 立体造形
「 天然木でつくる 」 -
hoge
![]()
![]()
3年 タイポグラフィー
「 オリジナルかなフォントの制作 」 -
hoge
![]()
![]()
3年 エディトリアル
「 マイナーフードキャンペーン 」 -
hoge
![]()
![]()
3年 ソフトウェア
「 Processingで繰り返し処理を有効活用したドローイングツールを作り、
それを使ってグラフィック作品を制作する。 」 -
hoge
![]()
![]()
3年 佐野プロジェクト
「 [ちょっとちがう] をテーマに100ビジュアル考える。 」 -
hoge
![]()
![]()
3年 菅プロジェクト
「 手に映して見る映像 」 -
hoge
![]()
![]()
3年 佐野プロジェクト
「 [ちょっとちがう] をテーマに100ビジュアル考える。 」 -
hoge
![]()
![]()
3年 ソフトウェア演習
「 Processingで繰り返し処理を有効活用したドローイングツールを作り、
それを使ってグラフィック作品を制作する。 」 -
hoge
![]()
![]()
3年 佐野プロジェクト
「 たまごかけご飯のお店をアートディレクションしてみる。 」 -
hoge
![]()
![]()
3年 佐野プロジェクト
「 たまごかけご飯のお店をアートディレクションしてみる。 」 -
hoge
![]()
![]()
3年 佐野プロジェクト
「 たまごかけご飯のお店をアートディレクションしてみる。 」 -
hoge
![]()
![]()
3年 柴田プロジェクト
「 ブックエンドまたはブックスタンド 」 -
hoge
![]()
![]()
3年 柴田プロジェクト
「 ブックエンドまたはブックスタンド 」 -
hoge
![]()
![]()
3年 柴田プロジェクト
「 ブックエンドまたはブックスタンド 」 -
hoge
![]()
![]()
3年 永井プロジェクト
「 何か×何か 」 -
hoge
![]()
![]()
3年 中村プロジェクト
「 会話 」 -
hoge
![]()
![]()
3年 菅プロジェクト
「 動きの標本 」 -
hoge
![]()
![]()
3年 菅プロジェクト
「 動きの標本 」 -
hoge
![]()
![]()
3年 長崎プロジェクト
「 曲げ加工 」 -
hoge
![]()
![]()
3年 長崎プロジェクト
「 曲げ加工 」 -
hoge
![]()
![]()
3年 長崎プロジェクト
「 LAMP 」 -
hoge
![]()
![]()
3年 長崎プロジェクト
「 LAMP 」 -
hoge
![]()
![]()
3年 パッケージデザイン
「 パッケージデザイン 」 -
hoge
![]()
![]()
3年 ソフトウェア
「 自分が得意なこととコンピューターが得意なことを掛け合わせて、心地よいインタラクティブ表現をつくる。 」 -
hoge
![]()
![]()
3年 形体制作
「 CLOCK 」 -
hoge
![]()
![]()
3年 コンストラクション
「 自立する形 」 -
hoge
![]()
![]()
3年 映像表現
「 実写を使ったイリュージョン映像 」 -
hoge
![]()
![]()
3年 タイポグラフィ
「 オリジナルかなフォントの制作 」 -
hoge
![]()
![]()
3年 立体造形
「 金属 」 -
hoge
![]()
![]()
3年 経験デザイン
「 「上野毛キャンパスごはん」の経験デザイン 」 -
hoge
![]()
![]()
3年 イラストレーション
「 好きなものを一つ選んで描く 」 -
hoge
![]()
![]()
3年 空間演出
「 にじむ境界 」 -
hoge
![]()
![]()
3年 インフォメーションデザイン
「 Conversation Piece 」
3・4年次の課題と作品
3年では、社会的な問題や生活から導きだされる焦点(Issue)から解決策や調和を生み出す仕組みの構築、そこに必要なモノ、環境、コミュニケーションなどの統合された全体をデザインすることを「プロジェクト」と呼び、担当教員ごとにゼミ形式で行う授業を通じて遂行します。そこでは教員固有の専門性を活かしたクロスレビューも実施します。更に幾つかの科目から自由に組合せを選択できる「デザイン演習」を通じてより専門性を深めていきます。4年次では、3年次に引き続き「プロジェクト」「デザイン演習」を行い、4年間の集大成となる卒業制作に取り組みます。